[ジャンル] 宗教・思想
31件 講座中 1~10件目を表示
-
おすすめ入会金必要
おもしろ仏像講座 ~見分け方、知っていますか? 4月4日スタート!
 おすすめ入会金必要
おすすめ入会金必要名刹で仏像と向き合い安らぎや感動が得られれば充分?もう一歩踏み込んで、仏像の持つ特徴を知り、種類が見分けられれば鑑賞力はアップするに違いないでしょう!チョットの予備知識が、今度仏像と接する時に新たな感動や発見が生まれます。課外講座にて、実際の生の仏像と接して、デスクワークで学んだことを肌で感じて頂きます。 初心者にも分かりやすく、今さら聞けない仏像の素朴な疑問を解決。鑑賞力が10倍アップします!長年旅行業界に携わった講師が海外のトピックスも、いろいろ紹介!<仏像のこころ>に接して新たな発見が生まれます! 【開 講 日】 【座学】4回 4月4日(金)から 原則 第1金曜日 13時30分~15時 4月4日(金) 仏像鑑賞の極意 如来編 5月2日(金) 仏像鑑賞の極意 菩薩編 7月4日(金) 仏像鑑賞の極意 明王・天部編 8月1日(金) 仏像鑑賞の極意 秘仏 編 【野外】2回(詳細行程は 実施月の前月に配布) 6月6日(金) 奈良国立博物館・超国宝展とならまち散策 法隆寺の観音菩薩像(百済観音像)・中宮寺の菩薩半跏思惟像などの国宝の数々が展示され、必見の価値あり。県庁展望台より、在りし日の平城京を俯瞰しまたならまちをも散策案内します。 9月19日(金) 白毫寺と新薬師寺散策 白毫寺からの展望は 奈良盆地が一望でき 遠く生駒山脈・金剛山脈をも展望できます。また閻魔大王像のチョット怖いお話もあり 新薬師寺の薬師如来像・十二神将は天平期の仏像の傑作!必見の価値があります。 ※拝観料については、当日集金します。交通費は各自、実費負担。 ※各行程は交通機関の都合、天候、道路状況等によりスケジュールの一部が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 ※行程は野外講座実施2週間前に書面にてご案内します。 ※雨天決行。荒天の際は教室受講に切り替える場合があります。
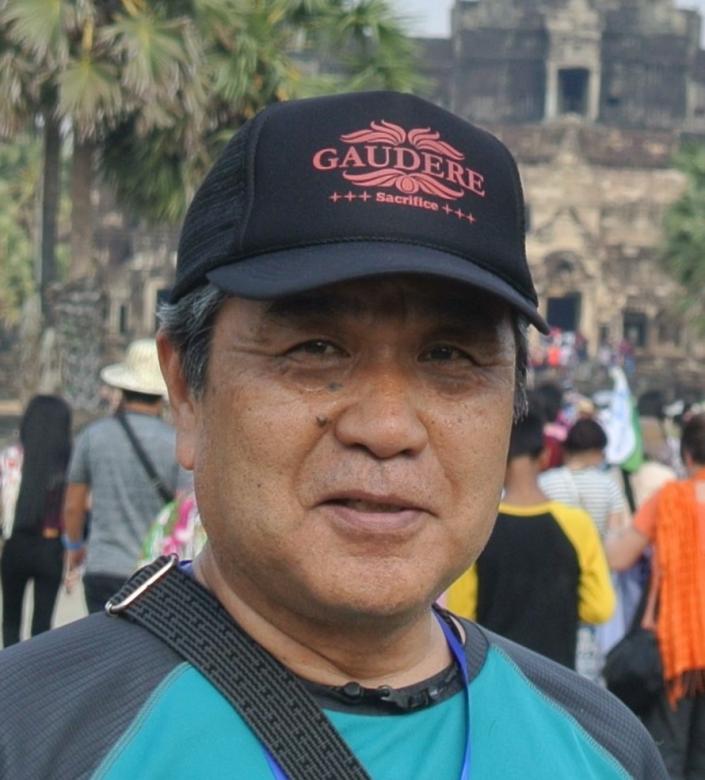
仏像ナビゲーター 樋口隆秀
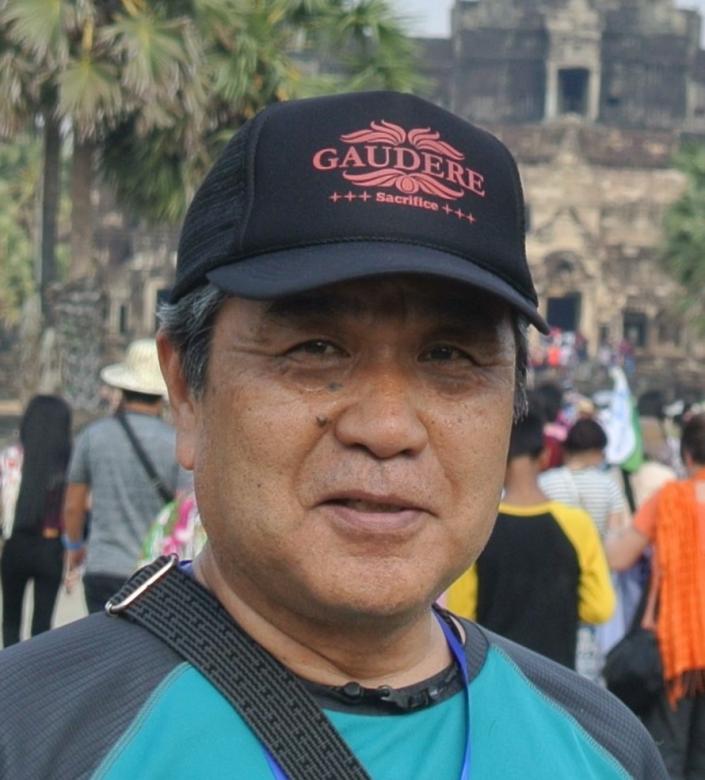
仏像ナビゲーター 樋口隆秀
-
Newおすすめ入会金必要常時入会可
聖徳太子は実在したか? その実像と謎
 Newおすすめ入会金必要常時入会可
Newおすすめ入会金必要常時入会可梅原猛は『隠された十字架—法隆寺論』で、法隆寺は聖徳太子の怨霊を封じ込めるために再建されたと言う。和の精神で『憲法十七条』を説いた聖徳太子が怨霊だったと度肝を抜いた。 これに対し、聖徳太子関係の史料は信用できないということから、聖徳太子実在論争が起きることになった。当時は実は蘇我王朝であり、大王は馬子であって、その皇子に厩戸王はいないから、『聖徳太子はいなかった』と在野の石渡信一郎は非実在論を展開した。大山誠一は、厩戸王の実在は認めながらも、何一つ聖徳太子と呼ばれるような業績をあげておらず、奈良時代の脚色によって祭り上げられたとする。 これらの論争をたどりながら、聖徳太子は果たして実在したのか、その実像に迫り、封印された謎を解明していきます。 【6回】 1.梅原猛著『隠された十字架』(1972年 新潮社) 法隆寺は聖徳太子の怨霊封じのために再建されたのか? 2.石渡信一郎著『聖徳太子はいなかった』(1992年 三一書房) 蘇我馬子は大王だったが、彼には厩戸王という王子はいなかった。 3.大山誠一著『聖徳太子の誕生』(1999年 吉川弘文館) 厩戸王はいたけれど、業績は僧道慈の捏造か? 4.関裕二著『聖徳太子は蘇我入鹿である』(1999年 ワニ書房) 蘇我入鹿の善行は聖徳太子として別人格にされ、本人は悪人にされた。 5.遠山美都男著『聖徳太子の謎』(2013年 宝島社) 厩戸王は何故天皇にはなれず、聖者に祭り上げられたのか? 6.石井公成著『聖徳太子―実像と伝説の間』(2016年 春秋社) 伝説化された聖徳太子から虚飾を除くとどんな実像が見えてくるのか?

哲学者 やすいゆたか

哲学者 やすいゆたか
-
入会金必要常時入会可
日本の神々 記紀神話から沖縄神話まで
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可日本の神々の伝承や祭祀儀礼、神社と聖地を理解することは、日本の本質に迫る道ではないでしょうか。 日本の生活文化として記紀神話から各地の伝承、沖縄神話まで幅広く取り上げ、古代から現代まで生きる宗教文化を知り、日本の心の鍵を解明します 内容例 ・「三輪山(蛇婿入り)型神話は、日本から大陸へ広がった」 ・「ワニと兎の神話は、インドネシアから日本へ伝わった」 ・「出雲大社の御本殿が48メートルあるのは、天空神を祭っていたから」 ・「伊勢の大神は、天照坐皇大神宮である」 ・「日本の悪神(スサノヲ、菅原天神)は、善神に大転換する」 ・「古事記の信仰の基本は、禊と祓えである」 ★1回で終わらない場合は、2回に渉ります

花園大学名誉教授、文学博士 丸山 顯徳

花園大学名誉教授、文学博士 丸山 顯徳
-
New入会金必要常時入会可
親鸞聖人の和讃を読む
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可本講座では、親鸞聖人の和讃を一首ずつ取り上げて、その短い言葉に込められた深い内容を紐解いていきます。 お経やその註釈書をもとにして、仏様や高僧方のお徳を讃え、法味豊かな七五調の歌にしたものを「和讃」といいます。 親鸞聖人は、生涯で五百四十首以上もの和讃を制作されました。中でも『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』は三帖和讃と呼ばれ、浄土真宗の法義が余すところなくおさめられていると言われています。 この三帖和讃を通して、阿弥陀仏のおこころを味わってまいります。 第一回 和讃概説 第二回 高僧和讃 源信讃① 源信僧都の略歴 「源信和尚ののたまはく」「本師源信ねんごろに」 第三回 高僧和讃 源信讃② 源信僧都の教義(報化二土) 「霊山聴衆とおはしける」から「極悪深重の衆生は」まで 第四回 高僧和讃 源空讃① 源空聖人の略歴①(立教開宗) 「本師源信世にいでて」から「承久の太上法皇は」まで 第五回 高僧和讃 源空讃② 源空聖人の教義(信疑決判) 「諸仏方便ときいたり」「真の知識にあふことは」 第六回 高僧和讃 源空讃③・総結 源空聖人の略歴②(ご臨末) 「源空光明はなたしめ」から「本師源空命終時」まで 高僧和讃総結 「五濁悪世の衆生の」

浄土真宗本願寺派吉祥寺住職、行信教校講師、本願寺派宗学院研究員、本願寺派布教使 西村一樹

浄土真宗本願寺派吉祥寺住職、行信教校講師、本願寺派宗学院研究員、本願寺派布教使 西村一樹
-
New入会金必要常時入会可
釈迦信仰 VS. 阿弥陀信仰 インド大乗仏教の実態を探る
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可インドでは大乗仏教が興起した時代、歴史上の人物であるゴータマ・シッダッタ(釈迦)とは私たちを導くための仮の姿であり、実は永遠の昔に仏になっていたと解釈された釈迦如来への信仰が盛んになりました。一方、極楽浄土において、いまも教えを説き続ける阿弥陀如来のもとへの往生を願う信仰も現れました。 本講座では、インド大乗仏教において、以上の釈迦信仰と阿弥陀信仰との間で起こったせめぎ合いの模様をご紹介したいと思います。 ① 4/22 釈迦の生涯 ② 5/27 舎利信仰 ③ 6/24 大乗仏教の仏たち ④ 7/22 永遠の釈迦 ⑤ 8/26 阿弥陀と極楽浄土 ⑥ 9/30(第5火曜) 釈迦か、阿弥陀か

龍谷大学講師 壬生 泰紀

龍谷大学講師 壬生 泰紀
-
Newおすすめ入会金必要常時入会可
昭和天皇の実録を読み解く ―宮内庁編纂資料から
 Newおすすめ入会金必要常時入会可
Newおすすめ入会金必要常時入会可4月11日開講!〈昭和天皇の実録を読み解く〉前期6回、後期6回。後期は10月10日から。 昭和天皇は、摂政4年、天皇62年と66年間、日本を代表する地位にあった。憲法上の位置は1947年を境に大きく変わったが、66年間政治に関わり続けた稀有の人といえる。 生前は公式会見での発言の外は侍従らのエッセイしか史料と言えるものはなかったが、没後は侍従らの日記やメモ、書簡に加え、天皇自らが史料を残す意味の記録にも熱心だったことがわかってきた。 宮内庁は、スタッフを増員して『昭和天皇実録』編纂に努力し、24年5カ月の歳月をかけて全61冊、1万2千頁の実録を完成させる。それを全19巻にまとめた『昭和天皇実録』が東京書籍から2019年までに刊行された。この『実録』を中心に、側近等の史料を加え、考察していく。戦前(戦中含む)1年、戦後1年の2年間で完結予定。 ・講義予定 ・講義予定 <戦前の前期> 第1回 誕生から幼少期―明治天皇の影響 第2回 皇太子―大正天皇の家族 第3回 英国王室と日本皇室 第4回 摂政から天皇へ 第5回 大元帥 第6回 山東出兵 <後期(10~3月)予定> 第1回 満州事変▽第2回 二・二六事件▽第3回 混迷の日本外交▽第4回 日中全面戦争▽第5回 太平洋戦争▽第6回 戦争終結へ

佛教大学歴史学部名誉教授 原田 敬一

佛教大学歴史学部名誉教授 原田 敬一
-
Newおすすめ入会金必要途中入会不可
さまざまな仏たち ブッダの教えを読みとく新シリーズ
 Newおすすめ入会金必要途中入会不可
Newおすすめ入会金必要途中入会不可人気講座の新シリーズです! 「ブッダの教えを読みとく」、4月からの新シリーズのテーマは「さまざまな仏たち」。釈迦牟尼、阿弥陀、薬師、阿閦(あしゅく)、弥勒など、仏教にはさまざまな「ほとけ(仏、如来)」がいます。歴史的に実在が確認されているのは釈迦牟尼だけです。なぜこんなにもたくさんの仏がいるのでしょう? 優劣はあるのでしょうか? 本講座では、名の知られた仏たちについて紹介し、これらの疑問に答えます。 2015年10月から開講している「ブッダの教えを読みとく」は、半年(全6回)ごとにテーマを変え、様々な角度からブッダの教えを解説し、仏教理解を深める講座です。 今シリーズは19期目となります。 第1回:過去仏、現在仏、未来仏 釈迦牟尼仏(釈尊)が誕生する前にも仏は存在しました。それを過去仏と言います。また、釈尊入滅後にも、仏は誕生すると考えられています。これを未来仏と言います。過去・現在・未来に在わす、仏について解説します。 第2回:釈迦牟尼仏 約2600年前に地球に誕生したと言われる釈尊の、前世も含めた生涯について解説します。 第3回:阿閦(あしゅく)仏 釈尊が教化した世界(私たちの住む世界)は「娑婆世界」と呼ばれます。この世界から遠く離れた東方にある「妙喜世界」と、そこを主宰する「阿閦仏」について解説します。 第4回:阿弥陀仏 娑婆世界の西方にある「極楽世界」と、その教主「阿弥陀仏」について、また東方・阿閦仏との関係について解説します。 第5回:薬師仏 娑婆世界の東方には、「浄瑠璃世界」もあります。この世界は、「薬師仏」が主宰し、阿弥陀仏の極楽世界の下請けのような役割を果たします。阿弥陀仏や同じ東方・阿閦仏との関係も含めて解説します。 第6回:弥勒仏 約56億7千万年後にこの世に誕生すると言われる弥勒仏は、今は兜率天(とそつてん)と呼ばれる神々の世界に住んでいると言われます。弥勒仏の役割は何か、今は兜率天で何をされているのか。弥勒をはじめとする未来仏について解説します。

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実
-
入会金必要常時入会可
インド神話に親しむ
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可~日本神話や仏教説話などとの比較~ インドのヴェーダ文献、二大叙事詩やプラーナ文献などには多くの神話が伝えられています。 これらの中には仏教説話との類似がみられ 、仏教を通して日本に伝わったものもあります。 インド神話と仏教説話などを比較することにより、神話の新たな面を知ることができます。 2025年4月~9月カリキュラム予定 日付 テーマ 詳細 4/25 ヴィシュヌの十大化身 未来の化身カルキン 5/23 ビーマとヒディンバーの結婚 ガトートカチャの活躍 6/27 無敵の司令官ドローナの死 クリシュナの策略 7/25 カルナの不思議な誕生 司令官カルナの死 8/22 アシュヴァッターマンの怒り 野営場での夜襲 9/26 ヤーダヴァ族の滅亡 ガーンダーリーの呪い ご参照 2024年10月~2025年3月 日付 テーマ 詳細 10/25 スンダラ・サムッダの出家 還俗させるために誘惑する遊女 11/22 ルーパヴァティーの秘密 二日目に彼女を抱くのは誰か 12/27 ジャティラの福徳と出家 長者の娘の不思議な出産 1/24 バラタ王の物語 鹿やバラモンへの転生 2/28 侮辱されたウンマディニー 焦がれ死にしたヤショーダナ王 3/28 ラーヴァニャヴァティーの誘拐 バラモンを殺したのは誰か

パーリ学仏教文化学会理事、元近畿大学教授 西尾 秀生

パーリ学仏教文化学会理事、元近畿大学教授 西尾 秀生
-
New入会金必要
哲学への誘い 5つの死を見つめて
 New入会金必要
New入会金必要避けて通れない死について考えてみませんか。 宗教学者、詩人、俳人、スパイ、思想家の5人はどのように捉えたのだろうか。彼らは果たして安らかに死を迎えられたのだろうか。 単に夭逝した俳人だけでなく、宗教学者自身が迫りくる死をどう捉えたか、またスパイとして刑死した人物は最後にどのような思いを持って刑場に赴いたか、稀代の奇人兆民は生死をいかに冷めた目で捉えようとしたか、そのような種々の思いや考え方をじっくり味わえたらと考えています。さて、あなたはどの人物の生死観に納得されるでしょうか。 ★2025年4月~9月カリキュラム予定★ 4月15日(火) 1回 宗教学者:岸本英夫の場合 5月20日(火) 2回 詩人:高見順の場合 6月17日(火) 3回 俳人:正岡子規の場合 7月15日(火) 4回 スパイ:尾崎秀実の場合 8月19日(火) 5回 思想家:中江兆民の場合 9月16日(火) 6回 結論:死をどう捉えるか

元宮崎学園短期大学教授、 大塚 稔

元宮崎学園短期大学教授、 大塚 稔
-
New入会金必要常時入会可
身体の哲学 ―哲学的心身論―
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可人類は、古代以来、人間の精神、心的活動と、身体の生理的活動を理解しようという探究を続けてきました。 西洋哲学では、一貫して心・精神の働きを中心に考察してきましたが、20世紀以降、心と同様に身体の働きも重視すべきであり、こころと身体は不可分であるという見解が主流となりました。 本講座では、20世紀後半以降の哲学的身体論、身体の哲学、および身体論の応用事例をわかりやすく概説していきます。 2025年4月~9月カリキュラム予定 第1回 4月19日(第3土):「心身問題と身体論」哲学的身体論 第2回 5月17日(第3土):「身体は物質なのか」現象学的心身論 第3回 6月21日(第3土):「身体の2つの感覚」所有者感覚、行為者感覚 第4回 7月19日(第3土):「環境に開かれた心」 生態学的アプローチ 第5回 8月30日(第5土):「建築する身体」エナクティビズム 第6回 9月20日(第3土):「身体を取り戻す」認知神経リハビリテーション ※8月16日は休館日のため、8月30日に変更しておりますのでご注意ください。

関西大学文学部哲学倫理学専修教授 三村 尚彦

関西大学文学部哲学倫理学専修教授 三村 尚彦















