297件 講座中 131~140件目を表示
-
おすすめ入会金不要常時入会可
色鉛筆画一日教室
 おすすめ入会金不要常時入会可
おすすめ入会金不要常時入会可身近な材料で無限の可能性と奥深さを表現できる色鉛筆画。 初めての方には大事なところをピックアップして教えします。 3月15日(土)、19日(水)、28日(金)からご都合のよい日をお選びください。 受講は1人1回です。定員各回6人。 15日、28日は「トスカーナの風景」、19日には「ブルーベリー」を描きます。 【持ち物】手持ちの色鉛筆(12色以上)、HBの鉛筆、消しゴム。スケッチブックは不要です。
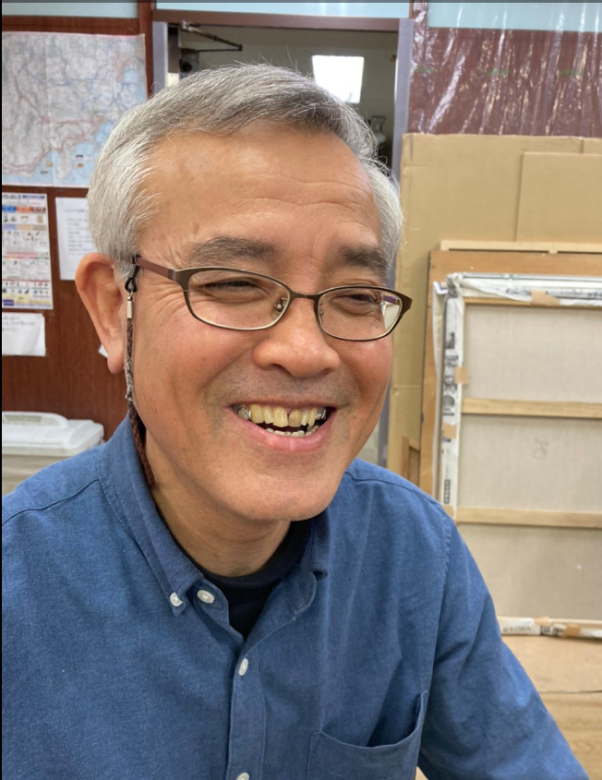
二紀会委員、洋画家 稲垣 直樹
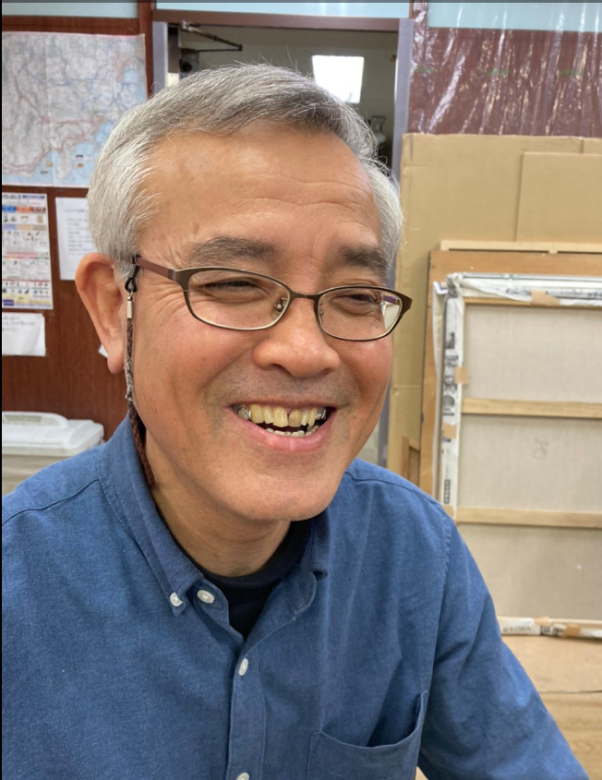
二紀会委員、洋画家 稲垣 直樹
-
入会金必要常時入会可
松尾芭蕉『おくのほそ道』を読む
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可「月日は百代の過客にして行きかふ年も又旅人なり」 壮大なスケールで始まる『おくのほそ道』。芭蕉は155日間の東北漂泊の旅で何を見つけ、何を伝えようとしたのでしょう。 古文書に興味のある方、旅行好きの方、歴史に関心のある方、俳句愛好者、そして少し立ち止まって人生を考えてみたい人も、一緒に『おくのほそ道』を読んでみませんか。本書は読めば読むほど、多くの事を語りかけてくれます。 2025年4月~9月のカリキュラム 4/24 石巻から平泉へ・中尊寺金色堂 5/22 尾花沢から 6/26 最上川 7/24 出羽三山へ 8/28 象潟と美女西施 9/25 荒海の佐渡 ※4クール(2024年4月~2026年3月)で完結予定です キーワード:奥の細道 おくの細道 おくのほそみち

元柿衞文庫学芸員 瀬川 照子

元柿衞文庫学芸員 瀬川 照子
-
入会金必要常時入会可
新古今和歌集の世界
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可王朝文学の精髄がすべて流れ込んでいる『新古今和歌集』をひもときながら、日本人の自然観と平安の雅を読み味わいます。 柿本人麻呂、小野小町、紀貫之、和泉式部、桜と月を愛した西行法師。さらに『源氏物語』を称揚した藤原俊成とその子・定家、若き万能の天才・後鳥羽上皇、『愚管抄』を著した慈円、賀茂の斎院であった式子内親王、似せ絵の天才画家・藤原隆信、『方丈記』の鴨長明ら、綺羅星のごとき歌仙たちの歌を集めた、美しい歌集です。 今期はいよいよ恋部の最終章、巻第十五「恋五」に入ります。 4/10 露に寄せた恋の歌 5/8 恋の涙 6/12 心変わり 7/10 恋の命 7/31(第5木曜) 別れと恋 9/11 鳥に寄せた恋の歌

京都産業大学教授 小林 一彦

京都産業大学教授 小林 一彦
-
入会金必要常時入会可
手相を学ぶ
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可手相は手の平に表れる線をみるだけではありません。 掌紋学・手の形・肌のきめ・手の厚さ等、さまざまな角度から、その人の本来の気質までも読み解きませんか。 私が皆さまにお伝えしたい手相学とは、優しく楽しく適格に、一風深く教えたいと思います。

日本運命学易占学院副学院長、日本五行易専門学院講師 吉岳 秀峰

日本運命学易占学院副学院長、日本五行易専門学院講師 吉岳 秀峰
-
入会金必要常時入会可
気持ちを伝える文章レッスン
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可思ったこと、伝えたいこと、残したいことって誰にもきっとあるでしょう。素直に文章にしてみませんか。書くのが苦手な人にも、もっとなめらかに書きたい人にも、マンツーマンで添削します。文はその人の個性であり、宝もの。ご自分なりの文を磨いていきましょう。 毎回、講座の前半は、読んだり話したり、日本語の楽しさ、豊かさに触れる時間。後半は作文タイム。時間がなくて課題作が出せない方も、ここで書いて提出できます。 作家や詩人、エッセイストらの文に触れ、さまざまな表現の引き出しを増やします。

コピーライター 田中 睦子

コピーライター 田中 睦子
-
入会金必要常時入会可
激動の古代朝鮮史
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可中国東北地方から朝鮮半島にかけては、紀元前1世紀から7世紀に至るまで高句麗・百済・新羅が勃興し、中国の諸王朝や倭と同盟・対立しながら、国家成長を遂げてきました。韓流ドラマで話題の『三国史記』や『三国遺事』などの史料より、古代朝鮮史の実像に迫っていきます。 ① 4/26 太武神王 ―創出された高句麗王 ② 5/24 新羅の祭祀と王権 ―始祖廟・神宮・寺院・宗廟 ③ 6/28 高麗福信 ―亡命高句麗人たち ④ 7/26 百済王善光 ―亡命百済人たち ⑤ 8/23 三千幢 ―新羅騎兵部隊の変遷 ⑥ 9/27 大欽茂 ―渤海隆盛の基礎を築いた王

京都府立大学文学部教授 井上 直樹

京都府立大学文学部教授 井上 直樹
-
入会金必要常時入会可
紫式部日記を読んでみよう 王朝文学の基礎とともに楽しむ
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可『紫式部日記』は、『源氏物語』作者として著名な紫式部の仮名日記です。紫式部は一条天皇中宮である、藤原道長の娘・彰子に仕えた女房でした。『紫式部日記』は、彰子の第一子となる敦成(あつひら)親王(後一条天皇)出産の記述から始まりますが、単なる記録に留まらない奥行きを持つ内容です。また、消息文と呼ばれる、同僚女房、そして一条天皇皇后の定子に仕えた清少納言についての批評などもあり、紫式部自身の心情や人間性も読み取れる興味深い作品です。 現代語訳のある初心者向けのテキストを用い、平安時代の華やかな宮廷生活や道長をめぐる政治状況にも触れながら、読んでいきます。 2025年4月~9月 カリキュラム 4月18日 四「一条院内裏へ」 1 紫式部の女房席次 5月16日 四「一条院内裏へ」 2 五節の童女たち 3 左京の君をからかう 6月20日 四「一条院内裏へ」 4 暮れゆく年 5 大晦日の事件 7月18日 五「消息体」 1 彰子女房をご紹介 8月29日(第5金曜) 五「消息体」 2 「彰子後宮女房がた、もっと風情を」! 9月19日 五「消息体」 3 中宮のご気性 4 引っ込み思案の弊害

京都女子大学非常勤講師・摂南大学非常勤講師 細川 知佐子

京都女子大学非常勤講師・摂南大学非常勤講師 細川 知佐子
-
入会金必要常時入会可
近世の天皇と朝廷
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可信長・秀吉の時代から江戸時代を経て、明治維新に至る三百年近くの時期を対象として天皇と朝廷の役割を探ります。 江戸時代の天皇と朝廷といえば、「禁中幷公家諸法度」によって縛られ、京都御所の中に封じ込められていたイメージがありますが、実際はどうだったのでしょう。 権力も財力もない天皇と朝廷が、三百年近くにわたって存続しえた理由について考えます。 ★2024年4月~9月のスケジュール★ [近世の天皇と朝廷Ⅰ] 1.4月3日(水) 近世の天皇と皇族 2.5月1日(水) 近世の朝廷と公家 3.6月5日(水) 朝廷官位制度 4.7月3日(水) 朝廷運営制度 5.9月4日(水) 朝廷と織田信長 ※8月休みとなったため、日程がずれます。 6.10月2日(水) 朝廷と豊臣秀吉 ★2024年10月~2025年3月のスケジュール★ [近世の天皇と朝廷Ⅱ] 7.10月23日(水) 平安京内裏と近世の禁裏 8.11月6日(水) 朝廷と徳川家康 9.12月4日(水) 朝廷と徳川幕府―関ヶ原合戦から元禄期― 10.1月22日(水)※朝廷と徳川幕府―享保から寛政時代― ★第4週へ変更 11.2月5日(水) 朝廷と徳川幕府―化政期から幕末― 12.3月5日(水) 明治維新と近代天皇制 ※カリキュラムは1年分表記。お支払いは、6ケ月分ずつです。

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古
-
入会金必要常時入会可
平家物語の人間像 ―平家公達の運命―
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす 『平家物語』冒頭のあまりにも有名なくだりです。私たちの魂を揺さぶり、一度耳にしたら忘れられないようなインパクトがあります。平家一門の栄華と滅亡を、仏教の因果律・無常観に基づいて描いた『平家物語』のなかには、たくさんの登場人物が行き交います。本講座では、そうした人々の人間像に注目してテーマを設定します。 今期(2025年4月~9月)は平家の公達を取り上げます。平家嫡流以外にも、『平家物語』には様々な平家一門の生きざまが描かれます。清盛が天皇家の外戚となり、人びとは公達とも称されましたが、その呼称とは裏腹に、動乱のなかで過酷な運命が課されていきます。そうした人物像を読み解いていきましょう。 4/22 宗盛の愚かさ 5/27 頼盛の選択・時忠の処世 6/24 忠度・経正の雅び 7/22 教経の武 8/26 重衡の罪と救済 9/30(第5火曜) 知盛の揺らぎと知

元同志社大学教授 源 健一郎

元同志社大学教授 源 健一郎
-
New入会金必要
ブッダから空海
 New入会金必要
New入会金必要ブッダは仏教の祖師というよりは「縁起の法則」を発見した天才と言える。しかしブッダ入滅後、インドではブッダの教えを議論するさまざまな派が誕生し、やがては大乗の諸部派が生まれることによって、ブッダの教えは原型とは異なるものへと変遷し、密教と呼ばれる新派が誕生することによって、インドでは仏教は衰退し、狭義ヒンドゥー教の時代に入って現在に到る。 仏教が中国を経て朝鮮半島を経由して日本に伝わった頃には、中国ナイズされた仏教をブッダの教えとして理解していたと言っても過言ではない。 奈良時代の仏教は学解仏教と言われる特徴を持っているが、平安時代になって空海が誕生する。空海がブッダの教えの原型と直結させる作業を通して、「縁起の法則」を軸とする本来のブッダの教えをよみがえらせたと言っても過言ではない。 そこで当講座では、ブッダの教えの本質を学び、その教えがいかなる形で空海の思想につながって行ったかというプロセスを主軸に考察していくことにする。

高野山大学名誉教授 前谷 彰(恵紹)

高野山大学名誉教授 前谷 彰(恵紹)















